はじめに
重度の障害を抱える方やそのご家族にとって、医療費の負担は大きな課題です。特に、心臓に関わる疾患で「S-ICD(皮下植込み型除細動器)」を植込んだ場合などは、身体障害者手帳1級が交付されることがあります。こうした方々が利用できる可能性があるのが「重度医療費助成制度」です。
この制度は、医療機関でかかった自己負担額を助成し、経済的な安心につなげる仕組みです。しかし、所得制限が設けられているため、すべての人が自動的に受けられるわけではありません。私も利用できるのかわからず、制度自体をあまり知らずつい最近申請し適用できることになりました。様々と調べていると所得制限の基準は全国一律ではなく、都道府県や市区町村ごとに異なる点にも注意が必要です。
今回はS-ICDやICDを植込んだ方は「重度医療費助成制度」が適用できる可能性もあるため、ご紹介です。
重度医療費助成制度の概要
「重度医療費助成制度」とは、重度の障害をお持ちの方や、特定の疾病を抱える方が医療機関でかかった医療費について、その自己負担分を助成する制度です。多くの自治体では、健康保険の自己負担(通常3割負担)のうち、本人が支払った部分を自治体が公費で助成し、実質的に無料または低額で医療を受けられるようにしています。
制度の対象は以下のような方が多く含まれます:
- 身体障害者手帳1級または2級の所持者
- 療育手帳A判定の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 先天性疾患や重度の慢性疾患を持つ児童 など
ただし、対象条件や助成の範囲は自治体ごとに異なります。
例えば「入院・通院ともに助成対象」とする自治体もあれば、「入院のみ対象」としているところもあります。また、自己負担に上限を設けて「1日◯円まで」「月◯円まで」としている自治体もあります。
さらに、多くの自治体では所得制限が設けられており、一定以上の所得がある方は助成を受けられません。そのため「重度障害者だから必ず無料になる」と思い込むのではなく、必ず居住地の制度内容を確認することが重要です。
所得制限の仕組み
重度医療費助成の判定には、「前年(または前々年)の所得」が基準になります。ここでいう「所得」は、給与の総支給額(年収)ではなく、給与所得控除を差し引いた後の「所得金額」です。
- 年収(収入):給料やボーナスの総額
- 所得:年収から給与所得控除を差し引いた金額
この所得が基準額以下であれば、制度の対象になります。つまり「年収が高いから対象外」とは一概に言えず、控除を差し引いた後の金額で判断される点が重要です。
都道府県ごとの違い
所得制限は自治体ごとに異なります。いくつか例を挙げると以下の通りです。
- 東京都:扶養なしで366万1千円
- 京都市:扶養なしで366万1千円
- 福岡市:扶養なしで366万1千円
- 広島市:扶養なしで169万5千円
- 大阪府:扶養なしで472万1千円
このように、同じ「重度医療費助成」と呼ばれる制度でも、基準は数十万~数百万円の幅があります。住んでいる地域によって受けられるかどうかが大きく変わる点は見逃せません。
調べた中で多い所得472万1千円は年収に換算すると?
多くの自治体で目安となる「472万1千円」という基準所得は、給与収入に換算するとおおむね年収650万円前後に相当すると考えられます。
例えば年収650万円の場合、給与所得控除を差し引くと所得は約468万円となり、基準内に収まるケースがあります。さらに障害者控除やiDeCo掛金の控除を利用すれば、判定所得はさらに下がり、対象となる可能性が広がります。
所得控除による影響
実際の判定では、次のような控除が適用されます。
- 障害者控除(特別障害者控除は40万円)
- 小規模企業共済等掛金控除(iDeCo掛金など)
- 扶養控除や配偶者控除
- 社会保険料控除
例えば、S-ICDを植込んで身体障害者手帳1級を取得した方は、特別障害者控除40万円を受けられるため、所得制限判定において有利になります。これにより、見かけの年収が高くても対象となるケースが少なくありません。
必ず受けられるわけではない
ここで強調しておきたいのは、重度医療費助成制度はすべての重度障害者が必ず受けられる制度ではないという点です。
- 所得制限を超えると対象外になる
- 自治体によって基準や対象障害が異なる
- 年度ごとに基準が見直される場合がある
- 年齢制限や他制度との関係で利用できないケースもある
たとえば、S-ICDを植込んで身体障害者手帳1級を取得したとしても、居住する自治体で所得制限を超えていれば対象外になることがあります。
確認のために必要なこと
- お住まいの自治体の福祉課・障害福祉課に確認
制度の最新基準は市区町村が定めています。必ず窓口で確認しましょう。 - 家族構成や扶養の状況を整理
扶養親族の人数によって制限額は大きく変わります。 - 所得控除の活用状況を把握
障害者控除やiDeCo掛金がどう反映されるかをチェックしておきましょう。
まとめ
- 重度医療費助成制度は医療費を軽減する有用な仕組みだが、全国一律ではなく自治体ごとに基準が異なる。
- 所得制限の代表例は「472万1千円以下(扶養なし)」で、年収にするとおおむね650万円前後が目安。
- S-ICDを植込んで身体障害者手帳1級を取得した場合は、特別障害者控除40万円が適用され、基準を満たしやすくなる。
- ただし、制度は必ず受けられるわけではなく、所得や地域の基準次第で対象外となる場合がある。
医療費助成を確実に受けるためには、必ずお住まいの自治体に確認し、最新情報を得ることが不可欠です。S-ICDを植込むと定期的な機器チェックや定期健診で一定の金額の受診費用が発生します。通院の回数が多いと少し負担が大きくなります。むやみやたらに使用することよくないかと思いますが、一定の使用をすることでしっかりと通院をして、健康維持を図ることが重要だなと感じています。制度を正しく理解し、自分や家族に適用できるかを早めに確認しておきましょう。
※本記事は令和7年9月末の情報を元に作成しています。所得制限の金額や各種制限は各自治体に確認をお願いします。
年収想定についてもあくまでの目安で記載しています。個々の状況によって異なるため、ご注意ください。





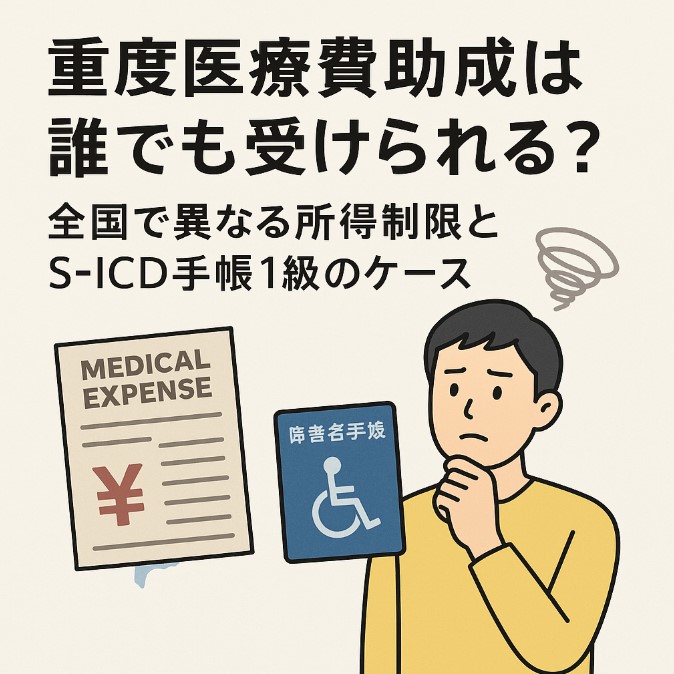


コメント